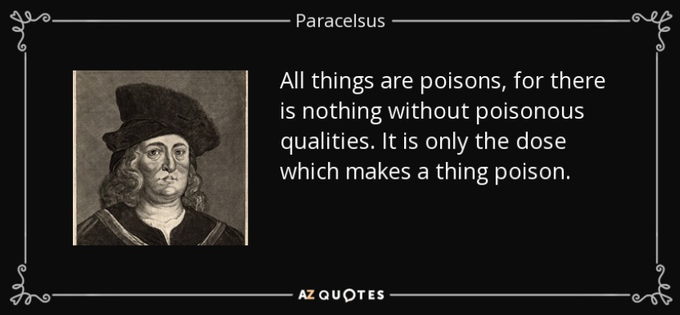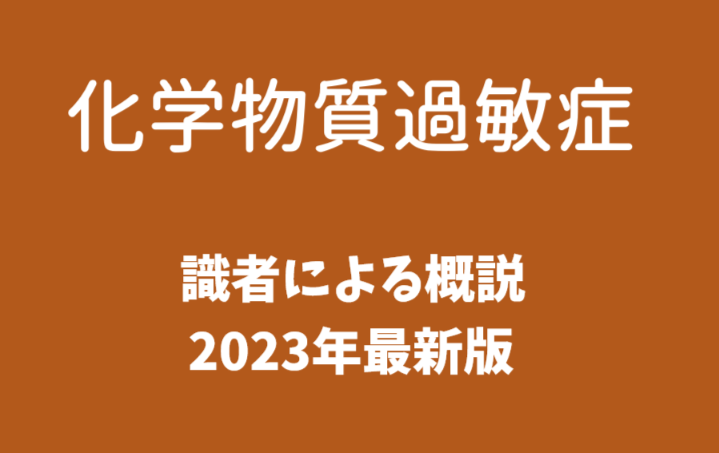
Multiple chemical sensitivity: It's time to catch up to the science(2023)「化学物質過敏症:科学的に解明され始めてきた」という論文の翻訳です。
「2023年 化学物質過敏症研究の最前線 1/7」の続きです。
翻訳文責:
一社)化学物質過敏症・対策情報センター
代表理事 上岡みやえ
3.化学物質過敏症(MCS)とは
化学物質に過敏な人はたくさんいます。
喘息患者では、最大で60% の人に、香水や洗剤の匂いによって症状が誘発されます。片頭痛患者の70% は、香水、塗料、ガソリンの匂いによって頭が痛くなると報告されています。
興味深いことに、片頭痛と喘息は併発することが多く、この方向性が異なる症状に共通するのは、化学物質臭への感受性です。
化学物質過敏症(MCS)は、通常は気にならないレベルの、低濃度の化学物質へのばく露によって、非特異的な症状を呈する後天的疾患について、もっとも頻繁に使用される病名です。
化学物質過敏症(MCS)は、環境過敏症、過敏症、環境疾患、環境不耐症、特発性環境不耐症、毒物誘発性の耐性喪失などと呼称されることもあります。
空気中の化学物質の濃度が、健常者には許容できるレベルであっても、かつては許容できていたレベルであっても、それらにばく露すると症状が出てしまうことが、化学物質過敏症(MCS)の特徴です。
3.1 化学物質過敏症(MCS)の症状
化学物質過敏症(MCS)の症状は、神経系、呼吸器系、胃腸系、心臓血管系で発生する可能性があります。
症状は多岐に渡ります。刺激性がある化学物質を吸入することで、症状が出ると考えられています。
一般的に報告される症状には、鼻水、息切れ、動悸、頭痛、目の灼熱感、喉の痛み、めまい、錯乱、疲労、過敏症、うつ病、短期記憶喪失、胃のむかつき、筋肉痛、関節痛などがあります。
最も多くみられるのは、中枢神経系(CNS) の症状、特に認知機能低下の訴えです。
3.2 化学物質過敏症(MCS)の定義
1980 年代から1990 年代にかけて、化学物質過敏症(MCS)をいかに定義するかが議論されはじめると、「化学物質過敏症(MCS)の症状は、低濃度の化学物質へのばく露に起因する」ことをベースに、いくつかの特性が追加されていきました。
現在、最も広く利用されているのは、カレンの定義(1987)と、化学物質過敏症のコンセンサス (1999) です。
カレンは、化学物質過敏症(MCS)を、一般集団に有害な影響を引き起こすとされる濃度をはるかに下回るの濃度の化学物質や、化学的に無関係な化合物に反応して、複数の臓器に再発性の症状を呈する後天性疾患と定義しました。
化学物質過敏症のコンセンサス (1999) は、Nethercott らによる先行研究に依拠しています。
「化学物質過敏症のコンセンサス (1999)」は、世界各国の患者にみられる症状の発現パターンを基にして(1999年の有識者会議にて)策定された基準です。この基準は、合計で数千人の化学物質過敏症(MCS) 患者の治療経験を有する北米の臨床医と研究者34人によって承認されました。
その後、「化学物質過敏症のコンセンサス (1999)」は、オンタリオ州保健省の資金提供を受けたトロント大学の環境過敏症研究ユニット (EHRU) によって検証されています。
化学物質過敏症:コンセンサス1999
① 慢性の経過をたどる
② 再現性をもって症状が出現する
③ 微量な化学物質に反応を示す
④ 関連性のない多種類の化学物質に反応を示す
⑤ 原因物質の除去で症状は改善される
⑥ 症状は複数の器官、臓器にまたがる
中枢神経障害の患者を含む対照群との顕著な違いは、化学物質過敏症(MCS)では、嗅覚が過敏、集中力が低下する、意識朦朧、思考力が低下する、ボーッとするなどが挙げられます。
2005 年、Lacour は、化学物質過敏症(MCS)を包括する定義とされる「化学物質過敏症のコンセンサス (1999)」 は、中枢神経障害 の 1 つとして規定すべきと提言しています。
3.3 疫学
「化学物質不耐症」は、化学物質への耐性が低いこと、あるいは化学物質にばく露したときに即反応が起きることだと説明されます。
米国、カナダ、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、オーストラリア、韓国、日本で行われた調査では、自分が化学物質過敏症(MCS)の症状を呈していることを自覚している人は、人口の9〜16%と報告されています。
一方、医師による確定診断を受けた化学物質過敏症(MCS)は、人口の0.5 ~3.9% と、低い率にとどまっています。
中年女性の罹患率が高いことが知られています。
米国では、2018年までの10年間で、自覚症状を呈している患者は200%増加して26%になりました。医師の確定診断を受けた患者は300%以上増えて13%に達しました。
患者が急増している理由として、化学物質や健康上の懸念に対する意識の高まり、化学物質過敏症(MCS)と診断できる医師が増えたこと、実際に有病率が増加していることなどが考えられます。
4 大陸にまたがって行われてきた研究では、化学物質過敏症(MCS)が公衆衛生上の大きなジレンマになっていることが浮き彫りになっています。
これは確かな疾病であり、そして、主観的な苦しみとして認識されています。
化学物質過敏症(MCS)は、一般大衆には問題がない濃度の、患者でさえ、発症前には問題がなかった濃度の化学物質へのばく露によって症状が引き起こされるという点で、特異的です。
科学界では、化学物質過敏症(MCS) と診断された人が、明らかな苦痛を感じていること、複数の機能障害を呈していることが、広く認識されています。
いま議論されているポイントは、ありふれた化学物質へのばく露によって引き起こされる症状が、生物学的に「本物」なのか、精神疾患による錯誤なのか、あるいは条件反射によるものなのか、です。
4.化学物質過敏症(MCS) の病因~論争の歴史
化学物質過敏症(MCS)に関する記述が、医学文献に初めて掲載されたのは、1960 年代初めのことです。
1990年代までに、複数の医療機関が、患者が主張する症状が、既知の病態生理学的メカニズムと一致しないことを根拠として、化学物質過敏症(MCS)という疾病は存在しないと表明しました。
それ以来、いくつかの国際的な研究が実施されてきました。
最近では、名だたる病院が「環境健康クリニック」という診療科を開設したり ( Women's College Hospital - Environmental Health Clinic Internet 2021 年)、権威ある科学機関が無香料ポリシーを策定したりしています。 ( Canadian Committee on Indoor Air Quality、2020 年)
化学物質に過敏な人のために、より安全な環境を提供しようとする病院も増えてきており(Flegel and Martin、2015)、化学物質過敏症(MCS) は配慮される権利を有する障害として法的に認められています。(カナダ人権委員会 2019年)
化学物質過敏症(MCS) を、明確な病態や症候群として説明できないからと、存在否定するのは誤りです。
化学物質過敏症(MCS)の存在を否定する医療機関はいくつかありますが、そうした意見は、20 年以上も昔のものです。
現在、化学物質過敏症(MCS)の臨床診断は、公表されている症例・症状にのっとって実施されています。診断に役立つバイオマーカーはありません。
化学物質過敏症(MCS)の定義については、いまだ見解が一致していないとする向きもありますが、「化学物質過敏症(MCS)のコンセンサス1999」は臨床医と研究者の合意に基づいて策定されており、カナダ・オンタリオ州政府(Ontario Ministry of Health and Long-Term Care)によって検証済みです。
1999年に策定されてから現在にいたるまで、「化学物質過敏症(MCS)のコンセンサス1999」に示されている6つの定義は反駁されておらず、化学物質過敏症(MCS)に関する調査研究において、一般的に使用され続けています。
過去 17 年間に出版された文献を系統的にレビューした総説論文(2018年)では、「カレンの基準」と 「化学物質過敏症(MCS)のコンセンサス1999」が、最も一般的に使用され、受け入れられている診断基準であるとされています。
化学物質過敏症(MCS) の診断は、論争を引き起こしやすく、今なお、症状が周囲環境へのばく露によって引き起こされているかどうかの真偽が問われています。
「特発性環境不耐症」は、病気の原因を「証拠なき思い込み」によって特定されることがないように、化学物質過敏症(MCS) に替わる病名として、20 年以上も前に提案されました。
症状を誘発するものが生物学的に真である場合、過敏症の症状についての生物学的、病態生理学的な要素を裏づける証拠が存在するはずです。
しかし、生物学的メカニズムを説明できる証拠は見つかっていないため、化学物質過敏症(MCS)は心因性の病であるという見解が存在し続けています。
4.1 低用量ばく露と毒性
伝統的に、毒性学の概念は、パラケルススが500年前に残した格言「毒性は用量で決まる」に依拠しています。
パラケルスス(1493-1541年)
つまり、有毒物質でも、ごく少量であれば無害となる可能性があり、無毒と考えられている物質であっても、過剰に摂取するば有毒になる可能性があるということです。
毒性学では、モデルシステムにおける用量反応の特徴を知るために、実験室での化学物質へのばく露研究が実施されます。
実際の生活環境における調査は、疫学の専門家によって行われます。急性および慢性のばく露において、何が悪条件となるのかを調べます。現実の生活においては、複数の汚染源に同時ばく露しており、ばく露状況は変化し続けています。
毒物のなかには、用量によって、異なる毒性を発揮するものがあることがわかっています。
たとえば、内分泌かく乱物質(EDC)として知られる化学物質は、微量ではホルモン作用に干渉する可能性がありますが、高用量では異なる影響を示す可能性があります。
ある内分泌かく乱物質(EDC)に高用量でばく露したときの影響がわかったとしても、それをもって、低用量でばく露したときの影響までは推定できないことが多いです。
内分泌かく乱化学汚染物質の主なメカニズムの 1 つは、受容体への結合です。
低用量でのばく露において、外来の化学物質が受容体に結合する親和性を持っている場合、それはアゴニスト(受容体応答の拡大)あるいはアンタゴニスト(受容体応答の減衰)として作用します。その結果、「細胞のシグナル伝達」ならびに「細胞の機能」が変化し始めるのです。
パラケルススの格言は単純すぎます。
毒性は複雑であり、変化に富んでいます。有害物質は短期的影響も長期的影響も有する「混合物」であり、私たちは、そうした「混合物」に生まれてから死ぬまでばく露し続けています。
そして毒性とは、こうした要素要件の総体として、作られるものなのです。