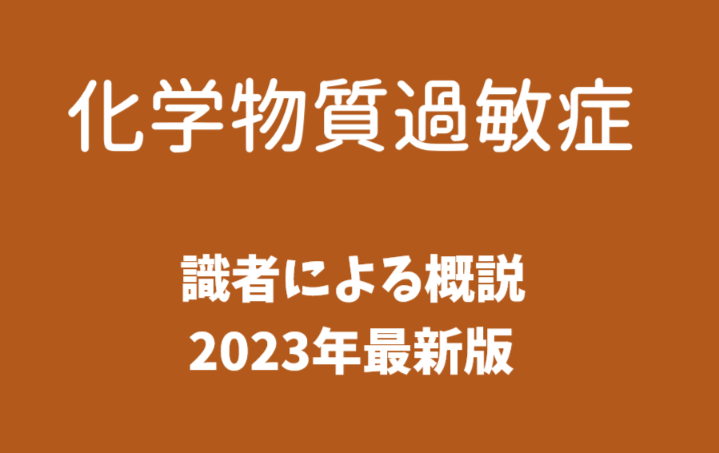
Multiple chemical sensitivity: It's time to catch up to the science(2023)「化学物質過敏症:科学的に解明され始めてきた」という論文の翻訳です。
2023年 化学物質過敏症研究の最前線 5/7 の続きです。
翻訳文責:
一社)化学物質過敏症・対策情報センター
代表理事 上岡みやえ
8.2 化学物質過敏症(MCS)の合併症と呼吸器系
化学物質過敏症(MCS)患者は、鼻炎、呼吸困難、咳などの上部および下部呼吸器症状が、化学物質へのばく露に起因すると考えていることが多いです。
8.2.1 化学物質過敏症(MCS)と咳嗽過敏症
カプサイシン吸入によって引き起こされる咳嗽(がいそう)は、化学物質過敏症(MCS)で最もよく観察される症状の1つです。
前述の通り、メタコリン吸入負荷試験で喘息が除外された場合でも、呼吸器症状を有する化学物質過敏症(MCS)患者では、カプサイシン吸入負荷試験によて咳嗽過敏症の症状を呈することが何度も実証されています。
咳は脳幹で制御される防御反射ですが、より高次の制御によって引き起こされます。咳をする前に、刺激が知覚されます。これを咳衝動 (UTC) と言います。
MRIによる脳機能検査によって、健康な被験者は、カプサイシン誘発性の 咳衝動 (UTC) 感覚が、大脳辺縁系や体性感覚皮質などのさまざまな脳領域の活性化と関連していることが実証されています。
ヒトの 咳衝動 (UTC) に関する研究のほとんどは、吸入による化学刺激に関するものです。
カプサイシンに反応する TRPV1 受容体を活性化する化学刺激は、機械感覚誘発性の反射性咳嗽とは対照的に、無意識には、または脳を切除した動物では、咳嗽を誘発しないことが注目されています。
化学感覚刺激が高次脳領域に中継されると気道刺激の知覚が誘発されますが、その結果としての咳嗽反応には、皮質から下位脳の呼吸中枢への下行性運動活動が含まれているからです。
8.2.1.1 咳嗽衝動と痛みが重複するメカニズム
健康なヒトがカプサイシンを吸入すると、体性感覚、運動、前頭前野、辺縁系皮質を含む、分散型の脳回路が活性化し、確実に 咳衝動 (UTC) が誘発されます。
これらの脳領域には、島皮質、ACC、一次感覚皮質、眼窩前頭皮質が含まれ、侵害刺激によって痛みが誘発されたときに活性化される領域と似ています。
カプサイシン吸入によって咳嗽過敏症が実証された被験者(化学物質過敏症(MCS)の基準を満たす被験者を含む)では、少なくとも部分的には末梢および中枢神経の感作の他、中帯状皮質、前島皮質、下前頭回など通常は咳嗽抑制を担う領域でのシグナル伝達が阻害されるために、咳衝動 (UTC) が上昇するという証拠を得られました。
咳衝動 (UTC) と痛みのメカニズムが重複していることは、痛み調整の条件付けによっても実証されています。
それは、体のある部位に、痛みを伴う条件付刺激を与えると、別の部位の痛みの知覚が軽減されるという現象です。
このことは注目するに値します。中程度の痛みの刺激 (親指に適用された圧力) による事前条件付けは、咳衝動 (UTC) の減少と、吸入したカプサイシンに対する誘発咳嗽数の減少の両方に結びついていたからです。
この観察結果は、MRIによる脳機能検査によっても裏づけられています。スキャン中に痛みの条件付刺激を与えると、カプサイシン吸入に関わる、特定の脳領域の活動が広範囲で減少したのです。
減少の度合いが、咳衝動 (UTC) の変化の度合いに比例することも確認されています。このことも、痛みと咳の経路が重複していることの証拠になります。
痛みと咳衝動 (UTC) のメカニズムにおける、もう一つの類似点は、中枢神経系(CNS)で活性化されたTRPV1受容体 と TRPA1受容体によって生じる変化です。
前述のとおり、TRPV1受容体 と TRPA1受容体 の活性化は、疼痛の知覚に大きな役割を果たしています。
これらの重複するメカニズムと、慢性疼痛障害と咳に相関性が見られるという発見は、符号します。
咳衝動 (UTC) と慢性疼痛が、神経解剖学的に、そして現象学的に重複していることを踏まえると、気道刺激から生じる感覚は、痛覚過敏を反映した感作の影響を受けると考えられます。
さらに、咳衝動 (UTC) も疼痛も、その しきい値が低いことを示すカプサイシン感受性も、化学物質過敏症(MCS)研究では、十分に文書化されています。
8.2.2 化学物質過敏症(MCS)と喘息
化学物質過敏症(MCS)患者は、喘息、疼痛障害、片頭痛を併発しやすいことがわかっています。
こられの疾病の患者は、化学物質臭に敏感であることが特定されています。
この他にも、喘息、慢性片頭痛、化学物質過敏症(MCS)には、いくつかの共通性があります。
8.3 化学物質過敏症(MCS): 合併症と他の臓器系
化学物質過敏症(MCS)は、多臓器障害と定義されています。最も影響を受けやすい臓器は神経系と呼吸器系です。
TRPA1 受容体は、神経系と呼吸器系の両方で発現していますが、結膜と角膜、喉頭、膀胱、上部消化器系と下部消化管系、心血管系においても、頻繁に同時発現しています。
これらの受容体は、泌尿器系、心血管系、胃腸系、呼吸器系に関連する、多様な生理学的機能と病態生理学的機能に関与しています。
たとえば、TRPV1受容体の感作は、化学物質過敏症(MCS)が併発しやすい機能性消化不良と過敏性腸症候群(IBS)に関与しています。
化学物質過敏症(MCS)は、アレルギー疾患を併発しやすいことも分かっています。
8.3.1 マスト細胞の活性化
マスト細胞が喘息やアレルギーの発症に関与していることは、数十年前から知られています。そしてマスト細胞には、神経系と免疫系を仲介する機能もあります。
いくつかの神経伝達物質と神経ペプチドによって活性化されるマスト細胞は、自然免疫と適応免疫の神経制御を可能にしています。
その反対に、マスト細胞は、神経伝達物質や神経栄養因子などのメディエーターも分泌しており、神経機能の急性活性化や、興奮性と表現型の長期的変化を引き起こすなど、神経機能に直接的な影響を及ぼしています。
マスト細胞は、脳内の血管とグリア細胞、そして中枢神経系のニューロンの近くに存在し、いくつかの炎症性メディエーターの放出につながるクロストークに関与しています。
マスト細胞は、生理的および病理的な疼痛経路における、重要な細胞調節因子でもあります。
注目すべきは、マスト細胞が、片頭痛の病態生理学において基本的役割を果たしていることと、マスト細胞の活性化によって、片頭痛や喘息など併存疾患に共通するメカニズムが説明できることです。
マスト細胞は、腸管ニューロンと密な関係にあることが多く、マスト細胞の活性化が、胃腸運動障害や、過敏性腸症候群(IBS)につながるようです。
実際、過敏性腸症候群(IBS)とマスト細胞の活動亢進が同時発生することは、頻繁に観察されています。
マスト細胞は、ヒスタミンによって作られる細胞です。ヒスタミンはTRPV1受容体を感作し、過敏性腸症候群(IBS)における内臓過敏症や腹痛を誘発する可能性があります。
TRPV1受容体も TRPA1受容体も マスト細胞上に発現しており、マスト細胞の活性化と脱顆粒に関与しています。
TRPV1受容体 と TRPA1受容体の感作が、化学物質過敏症(MCS)にマスト細胞活性化症候群が観察されることや、化学物質不耐性が増えていることの説明になる可能性があります。
喘息と過敏性腸症候群(IBS)の間には、双方向的な関連性が見られます。
これらの疾病に共通するメカニズムの1つは、マスト細胞の機能不全だと考えられます。
TRPV1受容体とTRPA1受容体は、喘息と過敏性腸症候群(IBS)の両方のメカニズムに関与しており、喘息、アレルギー、消化不良、過敏性腸症候群(IBS)は、化学物質過敏症(MCS)の併存疾患として知られています。
TRPV1受容体とTRPA1受容体 の機能を考慮すると、化学物質過敏症(MCS)の症状に関する生物学的証拠は強力なものとなります。
化学物質過敏症(MCS)に特徴的な、互いに無関係な多種類の化学物質に対する感受性は、TRPV1受容体とTRPA1受容体 によって説明できます。
TRPV1 受容体と TRPA1受容体の アゴニストを用いた、反論する余地がない脳機能画像検査によって、化学物質過敏症(MCS)の感作、感作されやすい傾向、感作されやすい部位、生物学的リスク要因、化学物質過敏症(MCS)が併発しやすい疾患の病態生理学的メカニズムなどが示されたのです。
アゴニスト(agonist)
生体内の細胞の受容体に結合し、神経伝達物質やホルモンなどと同様の機能を示す物質の総称。その多くが、受容体に結合できる特定の分子構造をもつたんぱく質からなる。
8.4 化学物質過敏症(MCS)と精神疾患
2012 年、カナダの健康調査を通して 21,977 人の成人データが収集され、化学物質過敏症(MCS)では、気分障害を発症し、深刻な精神的苦痛を感じる人の割合が非常に高いことがわかりました。
化学物質過敏症(MCS)と、パニック障害 、身体表現性スペクトラム障害、不安症、大うつ病(=気分障害の一つ、うつ病を指す)との関連性を示す研究は複数存在します。
7 件の研究では、化学物質過敏症(MCS) 患者は、健康な対照群よりも、生涯にわたる精神疾患を患う割合が高いと報告されています。
うち 2 件の研究は、化学物質過敏症(MCS) 患者の 80% に、長期にわたる精神疾患歴があると報告しています。
3 件の研究では、生涯にわたって精神疾患に苦しむ人が、化学物質過敏症(MCS)の約 50% にのぼることが示されています。
逆に言うと、化学物質過敏症(MCS)患者の 50% は、精神疾患を患っていないことを意味します。
2件の研究では、化学物質過敏症(MCS)患者の 70% 以上に、精神疾患の病歴がないことが報告されています。
わきまえておくべきは、上述の論文の執筆者たちが、「化学物質過敏症(MCS)の症状は、低濃度の化学物質へのばく露によって誘発される生物学的反応である」ことを理解していない点です。
将来への不安や生活の質の低下に対する悲しみを表明したにもかかわらず、症状が「一般的な医学的状態や物質の直接的な影響では十分に説明できない」という理由で、不安や抑うつ、または身体表現性障害と誤診された患者はどれほどいたでしょうか。
かつて、化学物質過敏症(MCS)の症状を、身体表現性障害とすることは、一般的でした。
医師が「この症状は医学的に説明できない」と評価することは、大きな問題です。
化学物質過敏症(MCS)の生物学的説明を考慮しない場合、診断の正確さを左右しうる病因について、医師の評価に偏りが生じる可能性があります。
悲しいことですが、身体疾患を進行中の精神疾患であると誤診されたがゆえに、早死にしてしまうケースは、珍しくはありません。
精神疾患は、身体疾患に起因する生物学的プロセスによって引き起こされる可能性があります。精神疾患も身体疾患も生物学的プロセスは同じであることは、事態をより混迷させる一因になっています。
化学物質過敏症(MCS)患者には、アルコール依存症やアルコール乱用の家族歴を有する可能性が高い一方で、患者本人は、飲酒量が少なく、アルコール不耐性であることが多いです。
化学物質過敏症(MCS)と精神疾患の間には、統計的な関連性が認められます。つまり、変数は偶然ではなく同時発生する可能性が高いこと、そして、病態の生理学的メカニズムやリスク要因が同じであることなどを意味しています。
特筆すべきは、複数の研究によって、大気汚染が精神衛生状態の悪化と関連していると実証されていることです。
系統的レビューとメタ分析によって、PM2.5 への長期ばく露と、うつ病や不安症との関連性が判明しています。
さらに、うつ病になった結果としての自殺や自殺企図、自殺念慮(じさつねんりょ)による救急外来受診は、大気汚染への短期的ばく露の増加と相関性があることが報告されています。
大気汚染と精神状態を結びつける共通メカニズムは、炎症と酸化ストレスである可能性が高く、これらは心理社会的ストレス要因によっても悪化する可能性があります。
不安障害のメタボロミクス研究では、酸化ストレスと炎症プロセスに関連する代謝物が判明しています。
メタボロミクス(metabolomics)
生体内の細胞や組織における、代謝物質の動態や反応経路を研究する学問分野。狭義にはメタボローム解析とよばれる代謝質の分離と同定技術を指し、広義には代謝反応の経路やその量的な解析を中心として、広く臨床医学や毒物学、創薬、栄養学などに応用する研究領域を含む。メタボローム解析。
デジタル大辞泉
タンパク質の酸化修飾は、不安障害やうつ病を含む、いくつかの精神障害の発症と進行における潜在的要因ではないかと疑われています。
系統的レビューとメタ分析によって、酸化ストレスとうつ病の関連性が判明しただけでなく、抗うつ薬の使用によって、酸化ストレスが軽減されることも判明しました。
重度のうつ病、不安症、心的外傷後ストレス障害の患者では、かなりの割合で、炎症を示すバイオマーカーが上昇していることから、炎症が、行動症状を引き起こす原因因子である可能性があります。
化学物質過敏症(MCS)と、不安障害、うつ病障害は、酸化ストレスおよび全身性炎症のメカニズムが同じです。
したがって、TRPA1 受容体 と TRPV1 受容体 の発現が増えることが、不安、気分の変化、文脈的な恐怖条件付け などの精神疾患の病因または病態生理に関与している可能性があります。
これまでの臨床研究によって、これらの受容体を抑制すると、抗うつ効果と抗不安効果があることが実証されています。
化学物質過敏症(MCS)と精神疾患の関連性を示唆する研究は、化学物質過敏症(MCS)の発症後かなり経ってから実施されているうえ、横断的であるため、そこから因果関係を特定することはできません。
もちろん、これらの関連性は、因果関係を意味するものではありません。
ストレスと不安は、他の多くの病状との関連性がみられます。
不安は、慢性咳嗽(呼吸過敏症)、喘息、片頭痛、機能性胃腸障害、炎症性免疫障害、神経変性疾患に見られる症状です。ここに挙げた疾患は互いに併発しやすく、化学物質過敏症(MCS)の併存疾患としても知られています。
ストレスと不安は、慢性片頭痛、喘息、化学物質過敏症(MCS)などで、複数のリスク要因が同じです。
慢性疼痛と感作による 咳衝動 (UTC) のメカニズムが重複しているように、これらの疾患のリスク要因とメカニズムは同じです。
それらが示しているのは、因果関係ではなく、根本的な病因だと言えるでしょう。