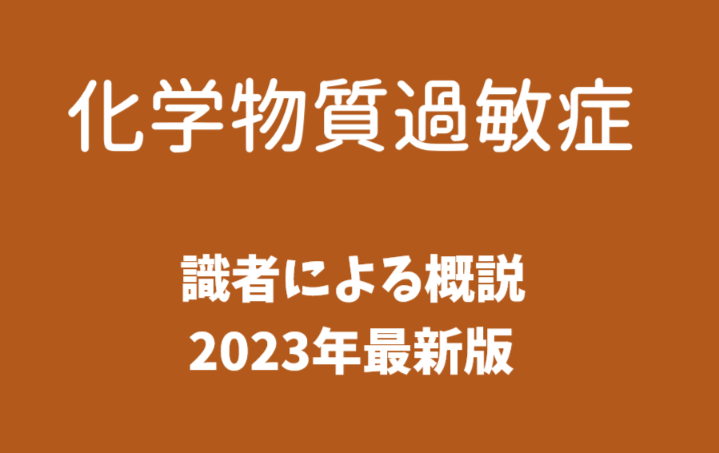
Multiple chemical sensitivity: It's time to catch up to the science(2023)「化学物質過敏症:科学的に解明され始めてきた」という論文の翻訳です。
2023年 化学物質過敏症の最前線 4/7の続きです。
翻訳文責:
一社)化学物質過敏症・対策情報センター
代表理事 上岡みやえ
8.化学物質過敏症(MCS)と併存疾患
「併存疾患/comorbidity」とは、通常、個人に複数の異なる病状が存在していることを指します。
「多疾患併存症/multimorbidity」は、少なくとも 2 つの慢性疾患を抱えていることを定義する用語です。
慢性疾患を患う人のほとんどは複数の病状を呈しています。その発生頻度は、加齢にともなって少しずつ高くなります。
「多疾患併存症」は、プライマリーケアにおける相談すべての78% を占めています。慢性疾患患者にとっては、「併存疾患」を抱えているのが普通という状態です。
疫学的にも、併存疾患が増えていることによって、還元主義的な単一疾患の枠組みによって設計されている、ほとんどの医療、医学研究、医学教育への疑問が呈されるようになってきています。
疫学:
人間集団を対象として、病気の原因や本態を究明する医学の一分野。感染症の原因や動向を調べる学問であったが、今日では、公害など広く健康を損ねる原因などを研究対象とする。
デジタル大辞泉
関連する危険因子や遺伝的、分子的、細胞の病態生理学的メカニズムなどが重なっている人に、病が併発する可能性が高いことは、その根底に、共通の病因経路があることを強く示唆しています。
片頭痛、喘息、アレルギー、湿疹、乾癬、不安、うつ病など、化学物質過敏症(MCS)の重症度に関連する、一連の併存疾患は、すでに特定されています。
化学物質過敏症(MCS)患者に併存疾患が頻繁に観察されることを考えると、化学物質過敏症(MCS)の併存疾患パターンを調べることで、その根底にある分子疾患メカニズムの理解が深まる可能性があります。
8.1. 併存疾患と神経系
中枢神経系(CNS)の複数の領域で広く発現し、多様な化学刺激に応答する、TRPA1受容体とTRPV1受容体は、シナプス可塑性に重要な役割を果たしており、そのことが、不安、うつ病、神経症状を含む、印象的な機能不全行動の数々に関与している可能性があります。
この分野は、痛みや神経性炎症に関連するため、広く研究されています。
TRPA1受容体を発現する感覚神経の大部分には、TRPV1受容体も発現しており、ともに、さまざまな有害刺激を統合しています。
化学物質過敏症(MCS) 患者では、それらの感作が確認されており、嗅覚以外の感覚機能障害が増加するという証拠もあります。
8.1.1. 化学物質過敏症(MCS)と慢性疼痛
カプサイシンは、化学物質過敏症(MCS)患者の痛みに対する感受性の増加を誘発します。
このことは、化学物質過敏症(MCS)患者が、線維筋痛症や他の慢性疼痛状態を併発することが多いとの説明に役立ちます。
この観察は、メカニズムが重複していることを示唆しています。
多量のカプサイシン吸入負荷試験を受けた被験者14人の脳機能の画像研究では、化学物質過敏症(MCS)患者は、健康な対照群よりも痛みのしきい値が低く、患者特有の神経回路には、内因性の機能的接続性が高いことが判明しました。
被験者は、化学物質過敏症(MCS)以外には問題がなく、肺活量も免疫グロブリンEレベルも正常、メタコリン負荷試験は陰性、精神障害の罹患歴もありませんでした。
化学物質過敏症(MCS)患者の脳機能画像検査によって、感作物質によって疼痛/特有性が検出されやすくなること、順化した物質との比較において、吻側前帯状皮質(rACC)の活性化が低いことが明らかになりました。
吻側前帯状皮質(rACC)は、侵害性疼痛の抑制にとって重要な領域でもあります。
化学物質過敏症(MCS)と慢性疼痛とは、(神経系における)興奮性の入力と抑制性の入力の不均衡をもたらすメカニズムを共有しているように見えます。そして、そのことによって、感覚の激しさが増強されているようなのです。
8.1.2. 中枢性感作
化学物質過敏症(MCS)は、中枢性感作の障害として説明されており、多くの器官系からの感覚入力、特に痛みが 中枢神経系(CNS)によって増幅される状態として定義されます。
中枢性感作では、中枢神経系(CNS)のニューロンの機能に混乱が生じます。
過敏になった中枢神経系ニューロンは、正常な状態のそれと比較して、発火しきい値が低く、受容野が拡大し、刺激に由来しない活動が延長され、反応が増強されます。
本質的に、中枢性感作は、感覚シグナル伝達の増幅につながる 中枢神経系(CNS)の構造ならびに機能の変化から成り立っています。
このような、感覚反応の強化には、将来の刺激に対する感度を高める神経可塑性が含まれます。 重要なのは、TRPV1 受容体が、複数の脳領域におけるシナプス可塑性に関与している点です。
併発しやすい慢性疼痛症候群の文脈で研究されてきた中枢性感作の特徴の 1 つは、全身に及ぶ感覚過敏です。
たとえば、線維筋痛症、慢性片頭痛、過敏性腸症候群(IBS)を患っている人は、聴覚、嗅覚、視覚刺激などの他の感覚様式に対する過敏性を訴える傾向があります。
騒音過敏症は、これらの疾患に共通する特徴であり、化学物質過敏症(MCS)を併発することが多く、化学物質過敏症(MCS)の症状も、騒音過敏症との関連性がみられます。
全身性感覚過敏症は、脳の前帯状皮質、中帯状皮質、島皮質、前頭前野皮質で構成される皮質神経回路の活性化に関連しています。
皮質神経回路の機能は、痛みに特化したものではありませんが、その後の高次の神経処理のために、特有な感覚刺激を抽出するという機能のほうが、より一般的なようです。
化学物質過敏症(MCS)患者では、この皮質神経回路が活性化することが観察されています。
興味深いことに、背側前帯状皮質( dACC)は、身体的痛みだけでなく、社会的痛み (例えば、社会的拒絶に反応したもの) の知覚 (または解釈) に関連する構成要素として、一連の神経回路に関与していると考えられています。
したがって、化学物質過敏症(MCS)に顕著な疼痛感受性は、有害な身体的および心理的情報を統合する 前帯状皮質(ACC) の構成する様々な要素の相互作用を反映している可能性があります。
痛みのない感覚を含む、あらゆる感覚的体験が、感覚に、予想を超えるレベルでの振幅をもたらし、時間や空間的感覚も増幅させることもあるのは、興奮の増加あるいは抑制の減少の結果としての中枢増幅を反映している可能性があります。
慢性疼痛障害では、中枢性感作によって、痛みを抑制する下降経路が阻害されます。そのため、興奮性入力と抑制性入力の不均衡が生じ、痛みの激しさ、疼痛しきい値の変化、損傷のない部位への痛みの拡散/放射が起こるのです。
こうした促進と抑制の不均衡は、片頭痛患者や線維筋痛症、その他の慢性疼痛疾患においても観察されます。
化学物質過敏症(MCS) においても、こうした不均衡が観察されることが判明しています。
8.1.3. 化学物質過敏症(MCS)と線維筋痛症
化学物質過敏症(MCS) と、線維筋痛症などの疼痛障害は、以前は問題がなかった刺激に対する有害反応を示すという点で似ています。
そして、TRPV1受容体 とTRPA1受容体 の両方が、病的痛みをもたらすメカニズムに大きく関与していることも、広く支持されています。
化学物質過敏症(MCS)研究に用いられているカプサイシンは、痛みを感知する求心性神経のTRPV1受容体を活性化するため、痛み処理の感覚メカニズムを研究するためにも使用されています。
健康な被験者への嗅覚刺激と同様に、痛みに対する一般的な反応においても「慣れ」が起こります。痛み刺激が継続的または反復的に繰り返されると、痛みと、痛みに関連する反応は減少します。
慣れは、吻側前帯状皮質(rACC)のシグナル増加に応答します。
化学物質過敏症(MCS)でも、その併存疾患とも言える線維筋痛症でも、感作物質と習慣化物質との比較において、そして健康な対照群との比較において、吻側前帯状皮質(rACC)の活性が低いことが観察されています。
8.1.4. 化学物質過敏症(MCS)と慢性片頭痛
片頭痛が引き起こされることと、周辺大気の粒子状物質とオゾン汚染へのばく露量の増加との間に関連性があるという証拠が呈されています。
周辺大気の他、屋内環境も、片頭痛に関与しています。片頭痛患者の 40% 以上が、香水や塗料などのニオイを片頭痛を引き起こす原因だとしています。
有病率研究では、片頭痛と化学物質過敏症(MCS)との間には、有意な関連性があることが証明されており、危険因子が重複していることや、病態生理学的なメカニズムが同じであることが示唆されています。
片頭痛においては、TRPA1受容体もTRPV1受容体も上方制御され、発作に関連する生理学的刺激によって活性化されます。
片頭痛のトリガー物質として認知されている様々な刺激物質は、実際には TRPA1 チャンネルの活性化因子です。
環境中に存在する刺激物を吸入すると、これらの受容体を介して三叉神経が刺激され、その後、三叉血管が活性化し、頭痛を引き起こしている可能性があります。
TRPA1受容体もTRPV1受容体も、どちらもカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)の機能に関連しています。
三叉神経の根神経節ニューロンから放出される カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)は、疼痛感受性と片頭痛に、大きな影響を与えています。
カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)によって、三叉神経の血管感作が引き起こされ、促進され、永続化される可能性があります。
三叉神経節で TRPV1受容体 を発現するニューロンのうち、少なくとも70% は カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP) も発現します。そして、TRPA1 受容体は、は 97% の確率で TRPV1 受容体 と共発現します。
片頭痛患者を対象とする機能的MRI研究では、三叉神経および頭の外側の侵害刺激に応答して、皮質の特徴的なパターン、皮質下の活性化、そして痛みの生成が示されました。
これらは、感覚処理領域における非定型的な機能的接続性について、客観的な証拠となります。
片頭痛患者は、感覚刺激への過剰な神経反応を示します。感覚刺激に対する反応抑制は弱く、片頭痛発作の最中であっても、習慣化反応がありません。
片頭痛患者に特徴的なのは、いくつかの疼痛促進領域の活性化が強いのに対し、疼痛抑制領域の活性化が弱いことです。
片頭痛患者の感覚処理の非定型的なのは、特に発作の合間において、繰り返される感覚刺激への生理学的慣れが欠如している点です。
生理学的慣れの欠如を伴う非定型的な感覚処理は、化学物質過敏症(MCS)にも観察されることから、共通のメカニズムであると示唆されています。
痛みの促進と痛みの抑制の不均衡は、片頭痛患者を、有害な刺激に対して、より敏感にさせている可能性があります。
こうした不均衡は、慢性片頭痛の一般的な症状である「痛覚過敏」と「異痛症」(異痛症:普段なら痛みを感じないような刺激が原因で、体の痛み、しびれ、不快感などの症状がおこる病気。別名アロディニア)を引き起こすとともに、中枢性感作の臨床的証拠にもなります。
不均衡は、慢性的な咳(=慢性咳嗽/まんせいがいそう)など、他の疾患でも観察されており、発症メカニズムに関する共通の証拠たりえます。
慢性疼痛と慢性咳嗽には、痛覚過敏症・過咳嗽症・異痛症・異咳嗽症など、臨床的特徴が重複する、様々な病状を含みます。
TRPA1 受容体 と TRPV1受容体も、中枢性感作も、痛みと咳の神経信号の調節に極めて重要な役割を果たしている下降性神経経路の阻害も、慢性疼痛と慢性咳嗽に影響を与えています。
慢性片頭痛は、酸化ストレスと全身性炎症に関連しており、化学物質過敏症(MCS) と同様、血液脳関門機能が破壊されるという証拠を得られています。
化学物質過敏症(MCS)と慢性片頭痛は、危険因子や機能不全の経路とパターンに共通性が見られます。
慢性片頭痛とインスリン抵抗性の関係性は、十分に文書化されていますが、化学物質過敏症(MCS)は、慢性片頭痛と同じインスリン抵抗性を有していることがわかっています。
慢性片頭痛のインスリン抵抗性は、ベータ細胞のインスリン産生が代償的に増加して高インスリン血症が引き起こされ、TRPV1受容体が感作されます。これにより髄膜求心路からの カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP) の放出が促進されて発現します。
インスリン抵抗性と 化学物質過敏症(MCS)は関連しあっています。
慢性片頭痛は、ビタミンDレベルの低下と、たんぱく質キナーゼの活性化 などの影響も受けます。
ビタミンDは、カプサイシンなど TRPV1受容体 の アゴニスト(=受容体に結合し、生体内物質と同様の細胞内情報伝達系を作動させる薬物)の刺激効果に拮抗し、TRPV1受容体によって媒介される三叉神経シグナル伝達を減少させます。
たんぱく質キナーゼ活性は、酸化ストレスおよび全身性炎症によって活性化され、TRPV1受容体 と TRPA1受容体 を感作する可能性があります。
この活性化によって、片頭痛患者によく見られる 中枢性感作 が促進されます。
さらに、ビタミンDは、TRPV1受容体 の感作に対するたんぱく質キナーゼの影響を軽減します。
化学物質過敏症(MCS)における、ビタミンDとたんぱく質キナーゼ活性化との関連性は、まだ検証されていません。
8.1.5 化学物質過敏症(MCS): 片頭痛と神経変性
体系的レビューとメタ分析により、片頭痛患者の脳は、複数の領域で灰白質体積が低下していること、その一部は頭痛発作の頻度に関連していることが確認されています。
化学物質過敏症(MCS)と同じ様に、慢性片頭痛も、神経変性を併発することがあります。
神経変性:
神経変性とは、何らかの原因により脳や脊髄の神経細胞が徐々に失われ、物忘れが多くなったり(認知症)、手足がうまく動かせなくなったり(運動障害)する病気です。 例えば、アルツハイマー病やパーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、ポリグルタミン病(ハンチントン病、脊髄小脳失調症)などがよく知られています。
近畿大学医学部 脳神経内科学教室
我々は、これまでに発表された論文を通して、化学物質過敏症(MCS)と、多疾患併存症としての神経変性の、どちらにも観察されている、病態生理学的メカニズムの存在を検証しました。
併存疾患を有することが多い慢性片頭痛、神経変性、化学物質過敏症(MCS)は、危険因子や発症メカニズムに、多くの共通性が見られます。 (表 3 を参照)
表3. 慢性片頭痛・神経変性・化学物質過敏症(MCS)の共通性
|
|
慢性片頭痛 |
神経変性 |
化学物質 過敏症 |
|
大気汚染へのばく露 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
解毒に関する遺伝子型 |
無し |
✔ |
✔ |
|
酸化ストレス |
✔ |
✔ |
✔ |
|
全身性炎症 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
BBBの破壊 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
慢性的痛み |
✔ |
✔ |
✔ |
|
中枢性感作 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
認知力の低下 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
TRPV1 受容体の上方調節 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
TRPA1 受容体の上方調節 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
脳質量の減少 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
嗅覚障害 |
✔ |
機能喪失 |
✔ |
|
嗅覚しきい値 |
正常 |
鋭敏化 |
正常 |
|
三叉神経機能不全 |
✔ |
無し |
✔ |
|
TRPV1 受容体の化学物質への過敏性 |
✔ |
無し |
✔ |
|
TRPA1 受容体の化学物質への過敏性 |
✔ |
無し |
✔ |
|
化学物質へのばく露による発病 |
無し |
潜行性 |
✔ |
|
化学物質へのばく露による症状の発現 |
>40% |
無し |
100% |
|
ビタミンD不足 |
✔ |
✔ |
未確認 |
|
たんぱく質キナーゼ活性 |
✔ |
✔ |
未確認 |