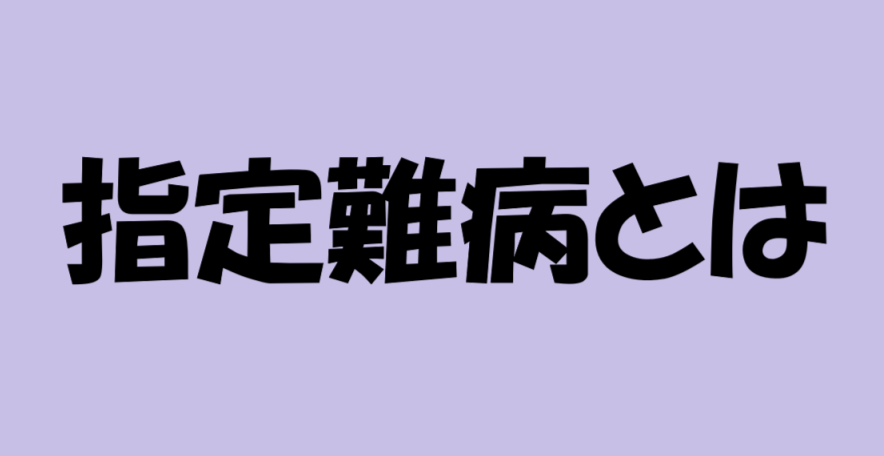
日本政府は、1972年の難病対策要綱を皮切りに、難病対策を進めてきました。
🩺指定難病とは?
✅ 厚生労働省によって定められた「難病」のうち、以下の条件を満たして**公費助成(医療費支援)**の対象となっている疾患のこと。
🧭指定難病の定義(4つの条件)
厚生労働省は、以下のすべてを満たす病気を「指定難病」と定義している。
① 発病の機構(原因)が不明、または治療方法が確立していない
→ 例:自己免疫疾患、遺伝性疾患、代謝異常など
② 病状が慢性に経過する
→ 長期にわたって治療が必要。完治しにくい。
③ 国が定めた一定の人数以下の患者数(希少性)
→ 日本全国で患者が概ね 人口の0.1%以下
(つまり約12万人以下)
④ 客観的な診断基準がある(医学的に明確に定義できる)
→ 誰が見ても「その病気だ」と確認できる状態
🎫指定難病になるとどうなる?
-
医療費の一部が公費で助成される(自己負担が軽減)
-
医療機関にかかる際の助成制度や、福祉・介護面のサポートも受けられる場合がある
-
自立支援や障害者認定の判断材料になることも
🧬例:指定難病に該当する病気
-
全身性エリテマトーデス(SLE)
-
クローン病
-
筋ジストロフィー
-
潰瘍性大腸炎
-
多発性硬化症
-
ALS(筋萎縮性側索硬化症)
…などなど、現在約340疾患以上が指定されている。(※2025年時点)
🩺指定難病の対象疾患数
1972年(昭和47年)
-
対象疾患数:8疾患(スモン、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、サルコイドーシス、再生不良性貧血、多発性硬化症、難治性肝炎)
-
日受給者数:17,595人
1973年(昭和48年)
1999年(平成11年)
-
対象疾患数:66疾患
2003年(平成15年)
-
対象疾患数:68疾患
2009年(平成21年)
-
対象疾患数:130疾患
2015年(平成27年)
-
対象疾患数:110疾患(難病法施行)
2019年(令和元年)
-
対象疾患数:333疾患
🩺指定難病・患者数の推移
指定難病受給者証所持者数の推移(平成17年度以降)
| 年度 | 受給者証所持者数 |
|---|---|
| 平成17年度 | 約78万人 |
| 平成18年度 | 約80万人 |
| 平成19年度 | 約82万人 |
| 平成20年度 | 約84万人 |
| 平成21年度 | 約86万人 |
| 平成22年度 | 約88万人 |
| 平成23年度 | 約90万人 |
| 平成24年度 | 約92万人 |
| 平成25年度 | 約94万人 |
| 平成26年度 | 約96万人 |
| 平成27年度 | 約98万人 |
| 平成28年度 | 約100万人 |
| 平成29年度 | 約102万人 |
| 平成30年度 | 約104万人 |
| 令和元年度 | 約106万人 |
| 令和2年度 | 約108万人 |
このデータは、難病情報センターが公開している「特定医療費(指定難病)受給者証所持者数」の統計に基づいています。
また、令和2年度の詳細なデータは、e-Stat(政府統計の総合窓口)で公開されています。
指定難病の種類も、受給者証所持者数も、年々増加しています。
③ 国が定めた一定の人数以下の患者数(希少性)→ 日本全国で患者が概ね 人口の0.1%以下(つまり約12万人以下)
という要件があるものの、潰瘍性大腸炎:患者数は約22万人と推測されるほど増えています。
なお、化学物質過敏症は、「指定難病」には指定されていません。
④ 客観的な診断基準がある(医学的に明確に定義できる)
という要件を満たしていないこと、診断できる医師が皆無に近いことが、その原因だと思われます。